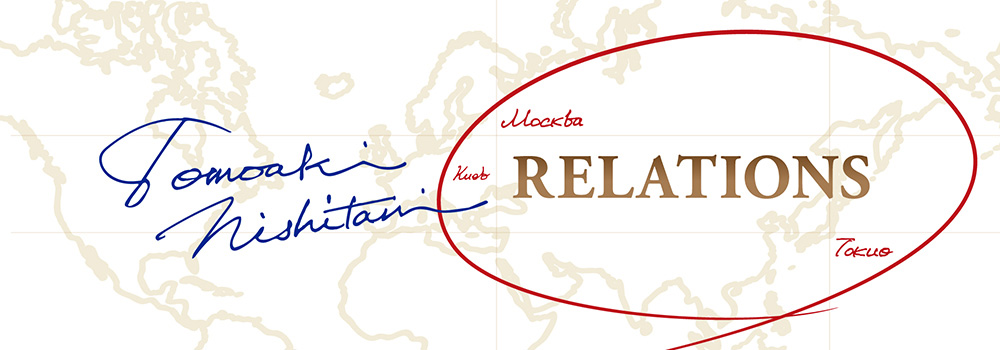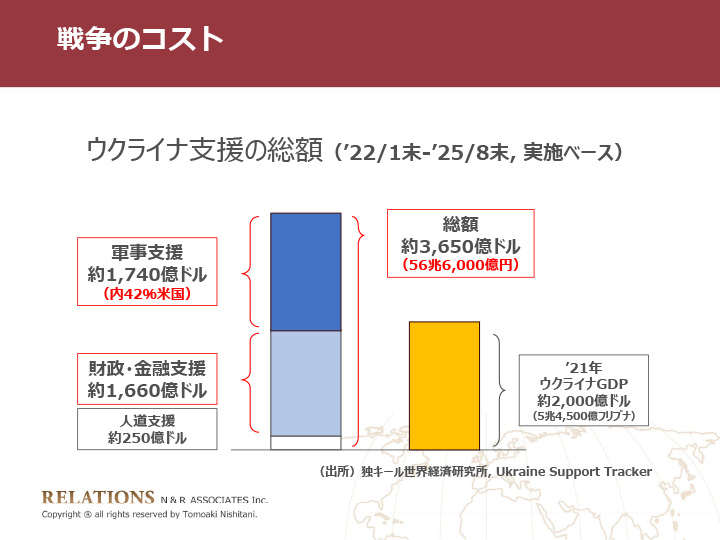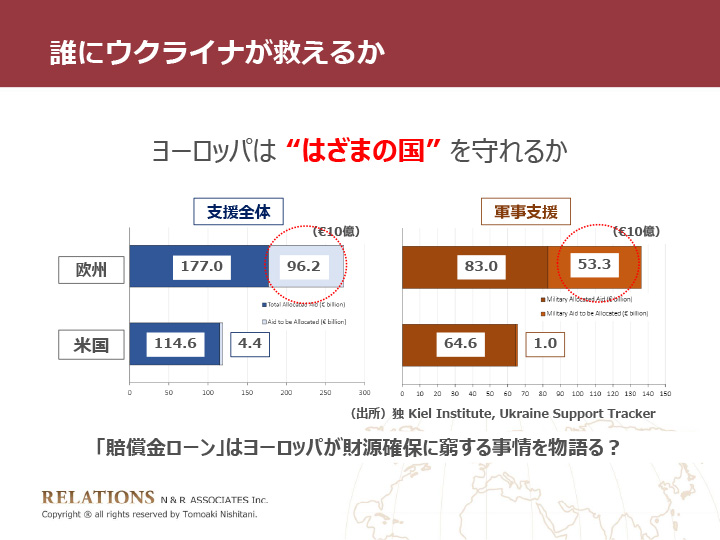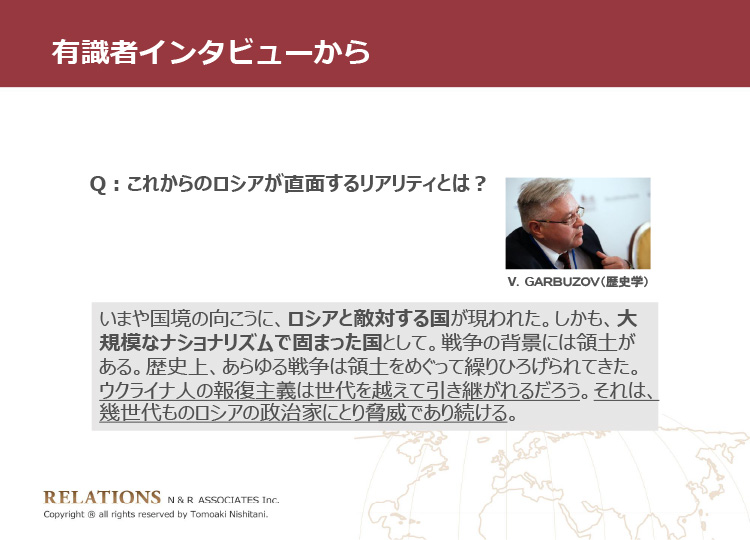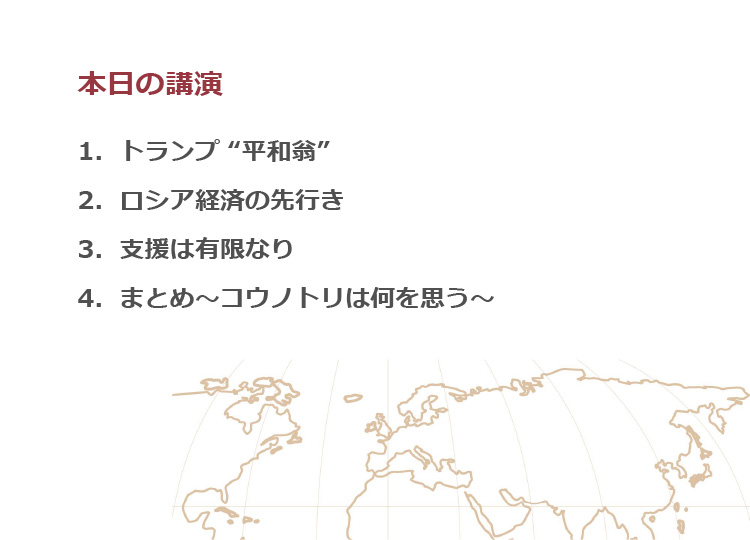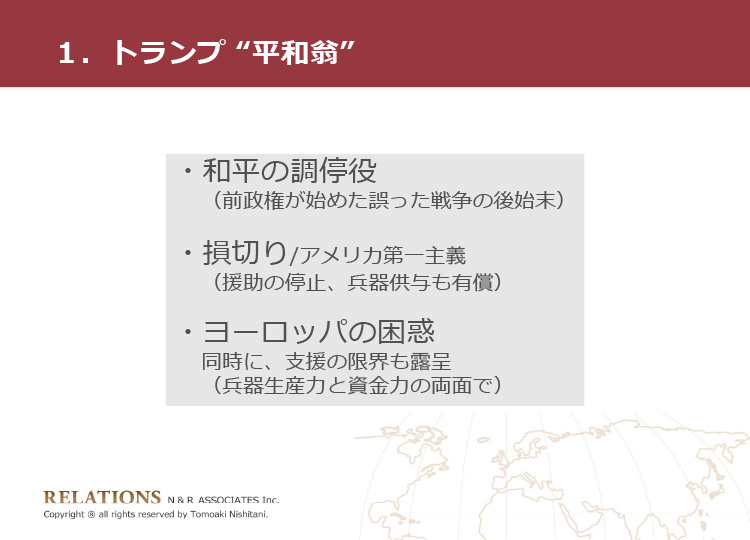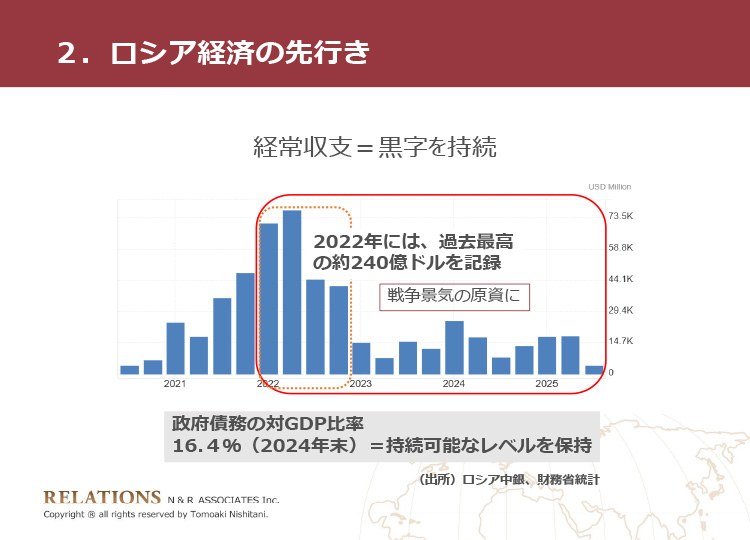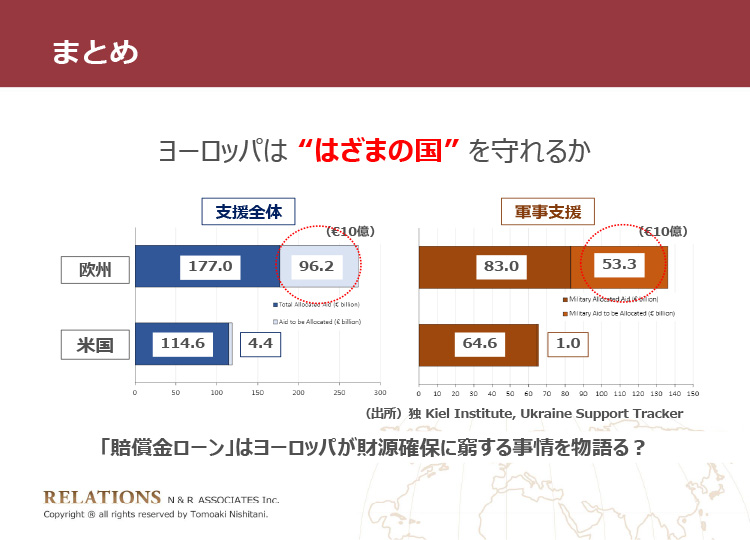プロフィール

西谷 公明(にしたに ともあき)
1953年生まれ
エコノミスト、
(合社)N&Rアソシエイツ 代表
<略歴>
1980年 早稲田大学政治経済学部卒業
1984年 同大学院経済学研究科博士前期課程修了(国際経済論専攻)
1987年 (株)長銀総合研究所入社
1996年 在ウクライナ日本大使館専門調査員
1999年 帰任、退社。トヨタ自動車(株)入社
2004年 ロシアトヨタ社長、兼モスクワ駐在員室長
2009年 帰任後、BRロシア室長、海外渉外部主査などを経て
2013年 (株)国際経済研究所取締役・理事、シニア・フェロー
2018年 (合社)N&Rアソシエイツ設立、代表就任
What's New
最新ニュース
-
コラボ
中国ウォッチ(41)
日中関係悪化と日本企業の戦略
-
講 演
JOIグローバルトピックセミナー
「ロシア・ウクライナ戦争-霞む和平」(抄録)
『海外投融資』(2026年1月号)
著 書
-
復 刊

ウクライナ 通貨誕生-
独立の命運を賭けた闘い岩波現代文庫、2023年1月
-
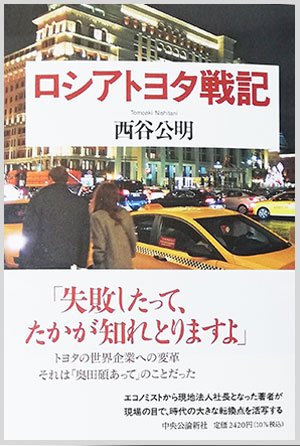
著 書
ロシアトヨタ戦記
中央公論新社、2021年12月
目次
プロローグ
第一章 ロシア進出
第二章 未成熟社会
第三章 一燈を提げて行く
間奏曲 シベリア鉄道紀行譚
第四章 リーマンショック、その後
エピローグ
あとがき -

著 書
ユーラシア・ダイナミズム-
大陸の胎動を読み解く地政学ミネルヴァ書房、2019年10月
目次
関係地図
はしがき-動態的ユーラシア試論
序 説 モンゴル草原から見たユーラシア
第一章 変貌するユーラシア
第二章 シルクロード経済ベルトと中央アジア
第三章 上海協力機構と西域
第四章 ロシア、ユーラシア国家の命運
第五章 胎動する大陸と海の日本
主要参考文献
あとがき
索 引 -
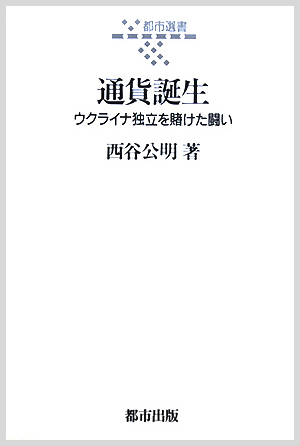
著 書
通貨誕生-
ウクライナ独立を賭けた闘い都市出版、1994年3月
目次
はじめに
序 章 ウクライナとの出会い
第一章 ゼロからの国づくり
第二章 金融のない世界
第三章 インフレ下の風景
第四章 地方周遊~東へ西へ
第五章 ウクライナの悩み
第六章 通貨確立への道
第七章 石油は穀物より強し
終 章 ドンバスの変心とガリツィアの不安
後 記
ウクライナ関係年表
西谷公明オフィシャルサイト
Tomoaki Nishitani official site